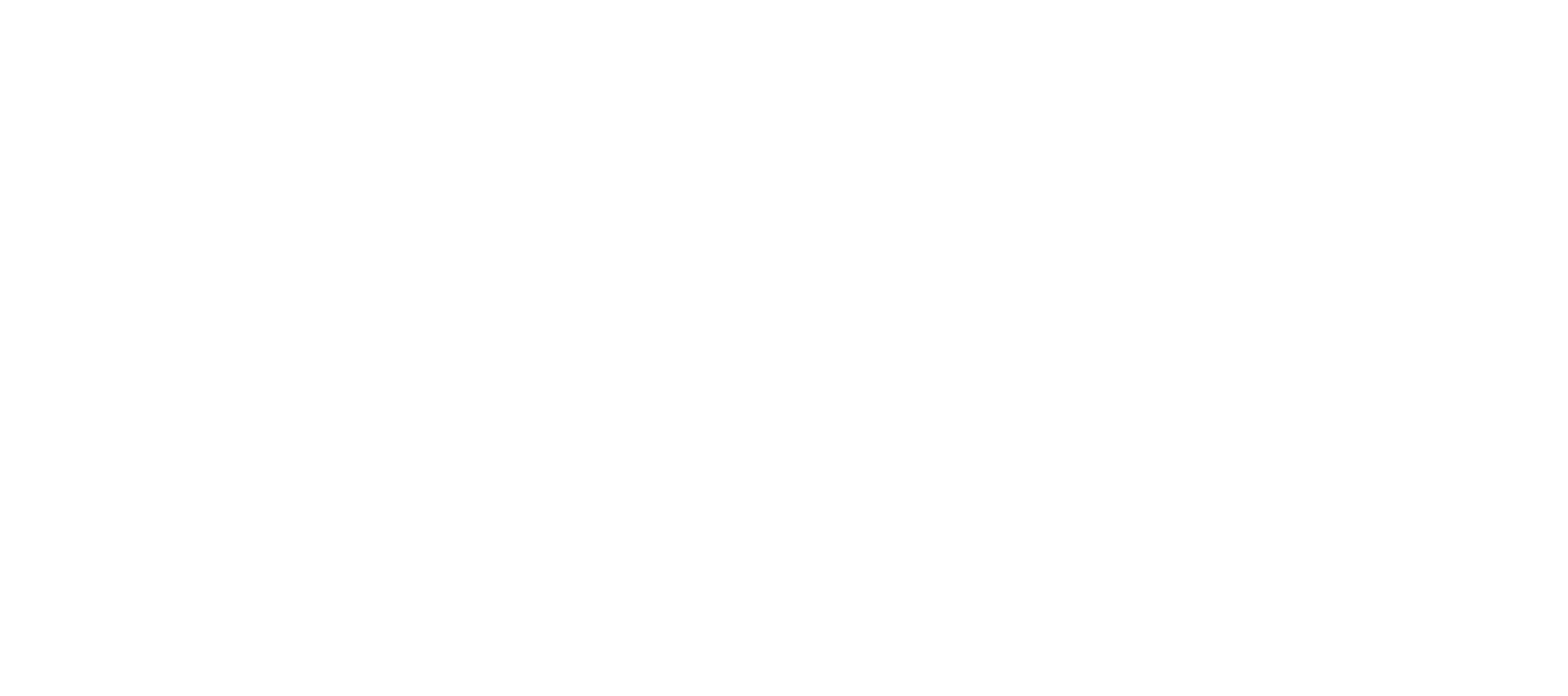
NEWS
お知らせ・募集要項

コラム
2025/08/17
長引く咳を診断するために行う呼吸機能検査について
咳はほぼ全ての呼吸器疾患で出るため、その原因は非常にたくさんの病気が考えられます。また、複数の病気が重なっていることもあり、一つの治療では咳が残ってしまうことも度々経験します。それでも、咳を鎮めるためにはその原因を調べることが大切です。今回は咳を引き起こす病気の診断に用いる検査として、呼吸機能検査(スパイロメトリー)について解説します。
呼吸機能検査は古くから用いられている検査法で、患者様に息を吸ったり吐いたりして頂くことで呼吸の能力を測定します。測定する項目として、肺活量、フローボリュームカーブ、努力性肺活量、1秒量、1秒率などがあります。
肺活量と努力性肺活量
肺活量は肺に入れることのできる空気の量です。つまり肺の容積、大きさと考えても良いでしょう。肺が膨らみにくくなる間質性肺炎、胸郭(肋骨や胸部の筋肉など肺の外側部分)の動きが悪くなる側湾症や胸膜炎後、呼吸筋が弱くなるALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経筋疾患で低い値となります。一気に息を強く吐き出して測定する努力性肺活量も同様ですが、強い呼吸努力で気道(気管と気管支をあわせた空気の通り道)が狭くなるCOPDや気管支喘息では、肺活量よりも努力性肺活量が低い値となります。努力性肺活量は間質性肺炎の状態評価としても大切なものです。
フローボリュームカーブ
大きく息を吸い込んだ後に一気に息を強く吐き出した時にできる呼気流速(息を吐く強さ)の時間変化を示すものです。カーブの形である程度病気を分類することができます。特にカーブが下に凹む形は気道が狭くなって息が吐き出しにくくなっていることを示すため、COPDや気管支喘息を考えます。ただし、咳の多い患者様では途中で咳き込んでしまうため正しい評価ができないこともあります。
1秒量
大きく息を吸い込んだ後に一気に息を強く吐き出した時に、1秒間に吐き出した呼気の量のことです。息の吐き出しにくさを示すもので、COPDや気管支喘息など気道が狭くなる病気で低い値となります。この値は病気の重症度として考えますので重要な指標です。なお、一気に吐き出した最大流量であるピークフローとも相関するため、喘息患者様が日常管理としてピークフロー測定を行うことも推奨されています。
1秒率
1秒量を努力性肺活量で割った値です。70%以下であれば気道が狭くなる状態があると判断されます。1秒量と違い、この値は病気の重症度として判断せず、あくまで気道が狭くなる状態があるかどうかを判断するもので、COPDの診断基準に含まれています。
気道可逆性検査
気管支を拡げる薬を吸入する前後で呼吸機能検査を行う方法です。気管支喘息は治療により呼吸機能が良くなるため、喘息かどうか診断するためには大切な検査です。薬剤吸入後に1秒量が200mlなおかつ12%以上良くなった場合は、喘息であると判断できます。逆にCOPDでは気管支拡張効果が弱く基準に届きません。薬剤吸入後に20分待ってから再度検査を行うため、検査に時間がかかります。
その他、ピークフローや、MMF(最大中間呼気流量)、V25(ブイドット25)などの指標もわかりますが、特に後者2つは個人差や再現性の幅が大きく、精密な評価には向かないとされています。
呼吸機能検査は限界まで息を吸ったり吐いたりするため、患者様にとってはつらい検査ですが、病気の状態を評価するためには欠かせない検査です。




